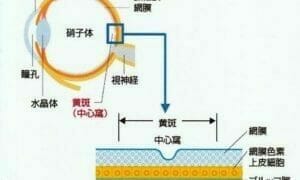 いろんな見え方の不都合に対応した眼鏡
いろんな見え方の不都合に対応した眼鏡 2019-01
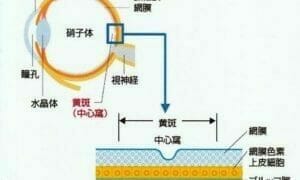 いろんな見え方の不都合に対応した眼鏡
いろんな見え方の不都合に対応した眼鏡  レンズについて
レンズについて 【実施例180811】不同視 遠視性乱視
課題:今の眼鏡が重たいので軽くズレないように。眼鏡の総重量は合計15gになり従来使用していた眼鏡の約半分程度まで軽減でき本来の目的を満足できた。強い内斜視が有るが眼科医と本人及び保護者と相談の上今後の課題。
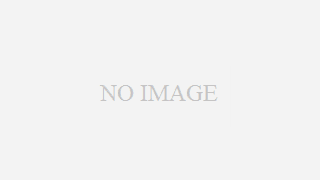 子供の弱視治療メガネ
子供の弱視治療メガネ 【実施例20180627】まさか我が子が!片目で見ていたとは・・・
一般に弱視治療は6歳までという一つの括りがありギリギリのステージであった。(別の説では最低8歳までと言われている。)弱視発見当初 矯正視力(眼鏡を掛け矯正した視力)0.1であったが約半年で0.4まで成長した。弱視治療増進のため眼科から「よく見える目を閉じるアイパッチ」を勧められ、当店サービスで提供したフレーム上に取り付けるアイパッチを使用されている。
 子供の弱視治療メガネ
子供の弱視治療メガネ 【実施例180414】子供メガネ 強度遠視性乱視
以前使用されていた眼鏡の重量はちなみに32g有ったが約半分以下に軽量化した。子供一般にありがちな眼鏡を押し広げかける使い方にも耐える弾力性のあるフレームにより変形することがなくなった事と軽量化によりズレ下がることが画期的に減った。目的とする視力向上がメガネを変えてから急速に向上したと保護者から報告を受けている。
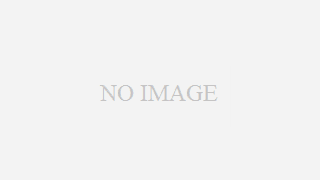 複視(斜視)矯正現場より
複視(斜視)矯正現場より 【実施例190119】内斜視+上下斜視
「内斜視+上下斜視」の実施例について解説。急にぼやけて見え遠くも近くも二重に見え不快、甲状腺に異常があるというお客様への対応例です。眼鏡のタイプは遠視性乱視、内斜視と上下斜視の複合。対応後のユーザーの反応も掲載しています。